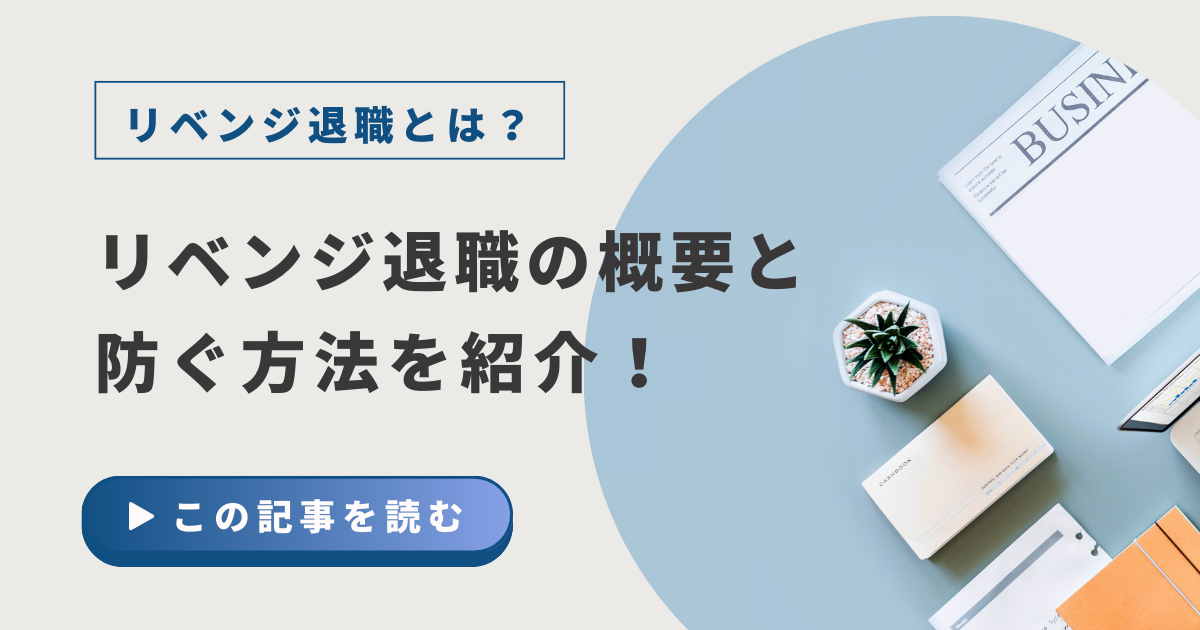
「ようやく採用できたと思ったら、またすぐに辞めてしまった…」
企業の採用担当者様、経営者様の中には、このような経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年、転職が一般化する中で、「リベンジ退職」、すなわち転職先の企業で再び不満を抱き、短期間で離職してしまうケースが増加しています。
この「リベンジ退職」は、企業にとって計り知れないリスクと損失をもたらします。
採用コストの無駄、組織全体の士気低下、企業イメージの損害…。
せっかく採用した優秀な人材が定着しないという問題は、企業の成長を阻害する喫緊の課題です。
本記事では、この「リベンジ退職」を未然に防ぐために、採用の入り口だけでなく、
退職前の企業側での「とっておきの対策」に焦点を当てて解説します。
具体的なアクションプランや、効果的な施策事例を交えながら、貴社の人材定着率向上と、採用活動の費用対効果を高めるための「最終奥義」をお伝えします!
- 1. 「リベンジ退職」が企業にもたらす甚大なリスク
- 2. リベンジ退職の実例から学ぶ「退職者の心理」と「企業の損失」
- 3. 「リベンジ退職」の根本原因を理解する
- 4. 「退職前」に企業がとっておくべき「とっておきの対策」
- 5. リベンジ退職を防ぐための「企業 対策」の「最終奥義」
- まとめ:「企業がリベンジ退職を防ぐには?」今すぐできる「対策」で、人材定着率を向上させよう!
1. 「リベンジ退職」が企業にもたらす甚大なリスク
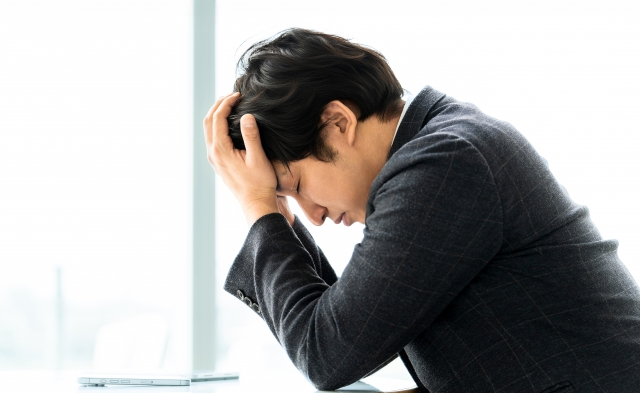
まずは、「リベンジ退職」が企業にもたらす具体的なリスクと、対策の緊急性を共有しましょう。
1-1. リベンジ退職とは?増加するその背景と実態
近年、新たな退職の形として「リベンジ退職」が注目されています。
リベンジ退職とは、会社への不満や仕返しといった意図を持って、意図的にトラブルを起こしたり、会社にダメージを与えたりしてから退職することです。
2021年以降、アメリカなどで、SNS上で退職理由や職場での不満を暴露する動画投稿が増加したことが、この傾向を加速させています。
アメリカの人材紹介会社の調査によると、2025年3月に3600人以上のアメリカの労働者を対象に調査を行ったところ、半数近い47%が、リベンジ退職の経験があると回答しています。日本でもその兆候が見られ、企業は「リベンジ退職 企業 リスク」に真剣に向き合う必要があります。
1-2. 顕在化する具体的なリスクと費用対効果の悪化
リベンジ退職は、金銭的な損失だけでなく、組織全体に深刻なダメージを与えます。
-
見えない採用コストの肥大化: 新しい人材を一人採用するためにかかるコストは、平均で約50万円から100万円以上と言われています。これが短期間で離職してしまうと、その費用は全て無駄になります。再募集にかかる広告費、面接や選考に費やす担当者の人件費、そして入社後の研修費用や育成費用も、全てゼロからの再スタートとなります。一般的なデータでは、早期離職者の再採用にかかるコストは、新規採用の1.5倍から2倍にも上ると言われています。つまり、リベンジ退職は、企業にとって「採用コスト削減」どころか、「採用コストの肥大化」という深刻な問題を引き起こすのです。
-
組織全体の士気低下と業務の停滞: せっかく新しい仲間が来たと思ったのに、すぐに辞めてしまう状況は、既存社員のモチベーションを低下させます。「また辞めるのか」「うちの会社には問題があるのか」といった不信感や不安を抱かせ、組織全体の士気を下げてしまいます。また、新しい人材に引き継ぐ予定だった業務が滞り、残された社員に負担が集中します。これにより、さらなる疲弊や離職を招く「負の連鎖」に陥る可能性もあります。
-
企業イメージの損害と法的リスク: 短期間での離職は、社外に対しても「離職率の高い会社」「働きにくい会社」というネガティブなイメージを与えかねません。特に、SNSでの悪評書き込みや誹謗中傷は、企業の採用活動だけでなく、顧客や取引先からの信頼にも影響し、ブランドイメージを損ないます。最悪の場合、データ削除や機密情報の持ち出しなど、意図的なトラブルによって裁判沙汰になる可能性もあり、「リベンジ退職 企業 リスク ゼロ」を目指すべき最優先課題です。
2. リベンジ退職の実例から学ぶ「退職者の心理」と「企業の損失」

具体的なリベンジ退職の事例を知ることで、その実態と企業が受けるダメージ、そして退職者の心理を深く理解しましょう。
2-1. データ削除による損害賠償事例
2025年1月、あるLED大手企業の元社員の男性が、退職する際に業務に関するデータを無断で削除したとして、会社が損害賠償を求めた裁判で、徳島地裁は男性に約577万円の支払いを命じました。
この元社員の男性は、最終出社日の前日に、勤務先の共有サーバー内の業務に必要なデータを含む、232個のフォルダが自身の退職日に削除されるよう、プログラムを設定しました。その後、企業側がファイルの消失に気付いた時には、復元可能期間が過ぎており、復旧できませんでした。この行為により、再開発やそのための新たな人件費が必要となり、会社は多大な損失を被りました。
これは、リベンジ退職が単なる感情的な行動だけでなく、企業に直接的な経済的損失をもたらす具体的なリスクであることを示しています。
2-2. 意図的な繁忙期退職と業務混乱の事例
入社2年目の銀行員時代、パワハラ被害を受けていたAさんのケースでは、Aさんは人事担当者に訴え、上司3人が異動になりました。
しかし、上司らに減給などの処分がされず、会社に不満を抱き、入社2年目で退職を決意します。その後、退職を決意したまま入社4年目に入り、営業成績も上がり、顧客の管理事務など重要な業務を担うなど、会社にとって必要な人材になったタイミングでリベンジ退職しました。
Aさんは退職のタイミングについて、「ただ退職するだけじゃ、全然何のダメージも与えられないと思い、周りが困るぐらい仕事ができるようになって辞めたら、会社へのダメージが大きいと思った」と話しています。Aさんの退職後、後任が新人しか見つからず、職場では混乱が起きました。
また、経営コンサルタントによると、給料など処遇に不満があった20代の公務員Bさんが、担当部署の繁忙期を狙って退職し、部署内が混乱したケースも報告されています。退職後、BさんはSNSに「ざまあみろ」と投稿しており、まさに「繁忙期を狙ったリベンジ退職」が判明しました。このような若手職員の増加は、「辞めるなら絶対に超繁忙期だよね」という意識が広がっていることを示唆しています。
2-3. SNSでの誹謗中傷による企業イメージ悪化事例
職場の人間関係に不満を抱いていたある重機メーカーの設計部署の20代男性従業員は、退職後に自身のSNSに、「人間関係が破綻している」「談合をしている」「下請けイジメをしている」と、会社が特定できる内容で誹謗中傷を投稿しました。
会社は男性従業員に対して、事実と異なる投稿の削除を依頼し、削除しない場合は法的措置を取ると警告しました。結果的に男性は投稿を削除しましたが、重機メーカーの人事担当者によると、「就活サイトで、ブラック企業という評判が広がってしまった」とのことです。
これらの事例は、リベンジ退職が、単なる早期離職に留まらず、企業の信頼性、ブランドイメージ、そして将来の採用活動にまで深刻な悪影響を及ぼすことを明確に示しています。
3. 「リベンジ退職」の根本原因を理解する

リベンジ退職を防ぐためには、その根本原因を深く理解することが重要です。
多くの場合、入社前の「期待値」と入社後の「現実」のギャップが、短期間での離職に繋がっています。
3-1. 採用ミスマッチの落とし穴
「採用 ミスマッチ 防止」は、リベンジ退職対策の根幹です。ミスマッチが発生する主な原因は以下の通りです。
- 情報不足・情報の偏り: 企業側が仕事内容や企業文化、職場の雰囲気などを正確に伝えきれていない、あるいは良い面だけを強調しすぎている。
- 応募者の期待値のずれ: 応募者側が企業や仕事に対して過度な期待を抱いている、あるいは自身のスキルや経験が活かせる場ではないと感じてしまう。
- 企業文化との不一致: 会社の価値観や働き方、人間関係などが、入社後に自身の価値観と合わないと感じてしまう。
これらのミスマッチは、入社後の不満へと繋がり、早期離職の引き金となります。
特に、一度転職を経験しているリベンジ退職者にとって、前職での不満が解消されない環境は、より早く次の転職を検討するきっかけとなるでしょう。
3-2. 転職者が抱える「前職の不満」と「再度の退職への抵抗のなさ」
リベンジ退職者の特徴として、前職での不満が解消されていないこと、そして一度退職を経験しているため、再度の退職への心理的ハードルが低いことが挙げられます。
彼らは「今度こそは」という強い期待を抱いて入社する分、その期待が裏切られた時の失望感も大きい傾向にあります。前職の不満が、転職先でも形を変えて現れた場合、彼らは「また同じことの繰り返しだ」と感じ、迷いなく次のステップへと進んでしまうのです。
4. 「退職前」に企業がとっておくべき「とっておきの対策」

では、これらの根本原因を踏まえ、企業がリベンジ退職を防ぐために、入社「退職前」にどのような対策を講じるべきでしょうか。
4-1. 採用における「期待値調整」の徹底
「期待値調整 採用 ギャップ 解消」は、入社後のミスマッチを防ぐ上で最も重要なプロセスです。
-
面接での「本音」の引き出し方:
- 良い面だけでなく、課題も包み隠さず伝える: 企業の強みだけでなく、現状の課題、職場の大変な点、残業の実態なども具体的に伝えます。
- 「逆質問」の時間を十分に設ける: 応募者が疑問に感じていることを解消し、企業への理解を深める機会を提供します。
- 具体的な質問例:
- 「前職で最も不満だったことは何ですか?それはどのように解決しようとしましたか?」
- 「当社の求人情報を見て、最も懸念に感じている点は何ですか?」
- 「入社後、どのような状況になったら『期待外れだった』と感じますか?」
- 「仕事でストレスを感じた時、どのように対処しますか?」
- 「キャリアプランについて、長期的な視点でどのように考えていますか?」
- 現場社員との交流: 面接だけでなく、可能であれば現場の社員とカジュアルに話す機会を設けることで、リアルな職場の雰囲気を知ってもらいます。
- ワークサンプルテストの導入: 実際の業務に近い課題に取り組んでもらうことで、スキルだけでなく、仕事への適性や向き合い方も見極めます。
-
企業文化や働く環境の「リアル」を伝える:
これらを徹底することで、「採用 ミスマッチ 防止 企業 革命」を起こし、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。
4-2. 戦略的な「オンボーディング施策」の実施
入社後の立ち上がりをスムーズにする「オンボーディング 施策 企業 効果的な」取り組みは、転職者の定着において極めて重要です。
- 入社前のコミュニケーション:
- 入社前の手紙やメール: 入社を歓迎するメッセージ、入社までのスケジュール、必要な持ち物などを具体的に伝えます。
- 社内SNSへの招待: 入社前から社内の雰囲気に触れ、既存社員との交流のきっかけを作ります。
- 入社直後の手厚いサポート:
- メンター制度・バディ制度: 新入社員一人ひとりにOJT担当やメンターをつけ、業務や社内ルール、人間関係の相談に乗ることで、孤立を防ぎます。
- 定期的な1on1ミーティング: 上司やメンターとの定期的な面談で、業務の進捗や困りごと、キャリアの相談などをきめ細やかにフォローします。特に、入社後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など、節目での面談は重要です。
- オンボーディングプログラムの導入:
- 具体的に定着率が向上した企業の取り組み事例(匿名):
- あるIT企業では、入社後3ヶ月間、週に1回のペースでメンターとの1on1を実施。業務内容だけでなく、プライベートの相談にも乗ることで、新入社員のエンゲージメントを高め、定着率が前年比で15%向上しました。
- 別の製造業の企業では、入社1週間で経営層とのランチ会を設定。経営者のビジョンや想いを直接聞くことで、社員の会社への愛着を育み、3年以内の離職率を大幅に改善しました。
これらの施策は、転職者が新しい環境にスムーズに適応し、会社の一員としての帰属意識を高める上で非常に有効です。
4-3. 既存社員への「リテンション戦略」の強化
リベンジ退職対策は、新規採用者だけでなく、既存社員へのリテンション戦略も重要です。既存社員が満足して長く働ける環境は、結果として新しい転職者の定着にも繋がります。
5. リベンジ退職を防ぐための「企業 対策」の「最終奥義」

多忙な採用担当者や経営層の方々から、
「分かってはいるけど、なかなか対策に手が回らない…」という声も聞かれます。
しかし、リベンジ退職は、「採用 失敗 例 から 学ぶ」べき喫緊の課題です。
費用対効果の高い対策を、今日から実践できる形で提案します。
5-1. 採用と人事の連携強化
採用担当者と人事担当者、そして現場のマネージャーが密接に連携し、情報共有を徹底することが「転職者 定着 企業 成功の鍵」です。
- 定期的な合同ミーティング: 採用段階での応募者の情報、面接での懸念点、入社後のフォロー体制などを共有し、連携を強化します。
- 採用基準・オンボーディングの共同策定: 現場のニーズを正確に把握し、ミスマッチのない採用基準や、実用的なオンボーディングプログラムを共同で策定します。
5-2. データに基づいたPDCAサイクルの確立
「人材 定着率 向上 奇跡の方法」は、データに基づいた改善の積み重ねです。
これらのデータから得られた知見を基に、採用プロセスやオンボーディング施策を継続的に改善していくPDCAサイクルを回すことが、リベンジ退職を防ぐ「最終奥義」と言えるでしょう。
5-3. 外部の専門家との連携も視野に
自社内でのリソースが限られている場合や、より専門的な知見が必要な場合は、外部の採用コンサルティングサービスや人事向け研修プログラムを活用することも有効です。
採用のプロフェッショナルは、多くの企業の「採用 失敗例から企業を救う」ノウハウを持っており、貴社の課題に合わせた最適な解決策を提案してくれるでしょう。
まとめ:「企業がリベンジ退職を防ぐには?」今すぐできる「対策」で、人材定着率を向上させよう!

「企業 リベンジ退職 防ぐ 対策」は、現代の採用市場において、企業が生き残り、成長していくために不可欠な戦略です。リベンジ退職による採用コストの無駄や組織への悪影響は、決して看過できません。
本記事では、リベンジ退職の根本原因と、企業が退職前にとっておくべき「とっておきの対策」として、以下のポイントを解説しました。
- 採用における「期待値調整」の徹底
- 戦略的な「オンボーディング施策」の実施
- 既存社員への「リテンション戦略」の強化
- 採用と人事の連携強化とデータに基づいたPDCAサイクルの確立
これらの対策は、「人材 定着率 向上 中小企業」から大企業まで、あらゆる規模の企業で実践可能です。今すぐにでも、貴社の採用プロセスや人事施策を見直し、リベンジ退職のリスクをゼロに近づける「リベンジ退職 企業 リスク ゼロ」を実現しましょう。
優秀な人材が定着し、会社が成長する「奇跡の方法」は、決して魔法ではありません。地道な努力と、この記事でご紹介した具体的なアクションプランを実践することから始まります。貴社の人材戦略が、より強固なものとなることを心より願っております。